リソソームとは
ヒトの細胞の中には核やミトコンドリアなど、たくさんの小器官があります。
細胞小器官は体を保つための大切な役割を、それぞれ持っています(図1)。
リソソームは細胞小器官のひとつです。
細胞内でいらなくなった老廃物などを、さまざまな種類の酵素を使って消化・分解するはたらきを持ちます。
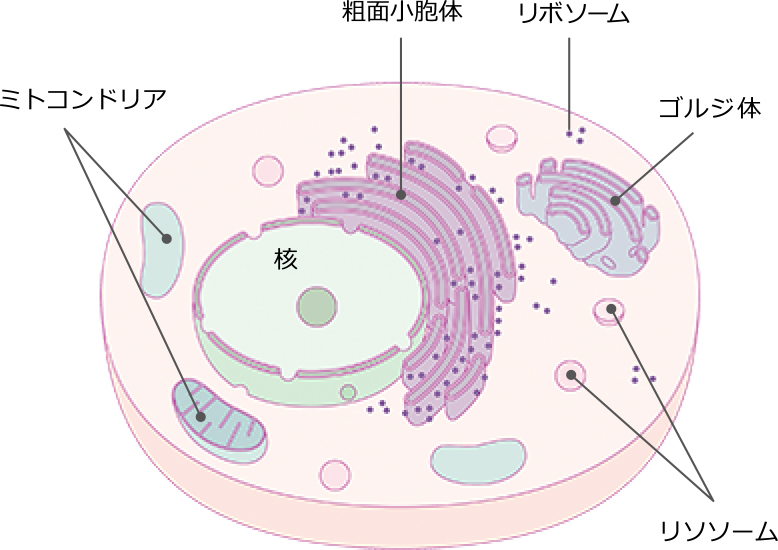
図1:ヒトの細胞
ライソゾーム病が発症する理由
ライソゾーム病になると、消化・分解を担う酵素が十分にはたらかず、本来分解されるはずの老廃物などがリソソーム内に溜まって(図2)、全身にさまざまな症状が現れるようになります。
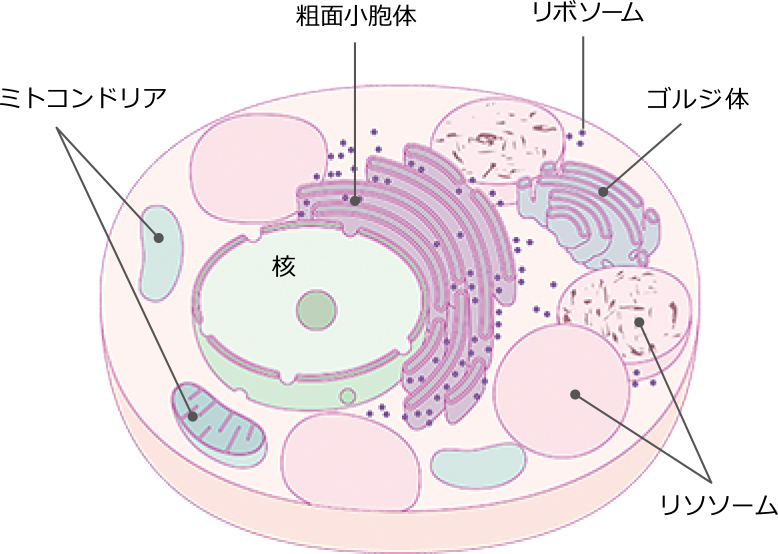
図2:ライソゾーム病の患者さんの細胞
ライソゾーム病には、どの酵素がうまくはたらいていないかによって、さまざまな種類があります。
α‐ガラクトシダーゼという酵素がうまくはたらいていない場合、「ファブリー病」になります。
| 病名 | はたらきにくい、量が足りない酵素 | 蓄積する物質 |
|---|---|---|
| ファブリー病 | α‐ガラクトシダーゼA | グロボトリアオシルセラミド (GL-3)など |
| ゴーシェ病 | グルコセレブロシダーゼ | グルコセレブロシド |
| ポンペ病 | 酸性α‐グルコシダーゼ | グリコーゲン |
| ムコ多糖症 (Ⅰ型:ハーラー/シャイエ症候群、Ⅱ型:ハンター症候群、Ⅶ型:スライ病など) |
ムコ多糖分解酵素 | ムコ多糖 |
表:ライソゾーム病の例
ファブリー病
生まれつき、α-ガラクトシダーゼ Aと呼ばれる酵素を十分に持っていないために起こります。
全身の細胞に糖脂質が蓄積するため、子どものときに手足の痛みや、汗をかきにくい、発疹といった症状が現れることや、大人になってから心臓の病気、腎不全などの病気が現れることがあります。
症状やその程度は人により異なります。
ポンぺ病
生まれつき、酸性α-グルコシダーゼと呼ばれる酵素を十分に持っていないために起こります。
この酵素は糖のひとつであるグリコーゲンの分解に必要です。酵素が不足して分解が出来なくなると、全身にグリコーゲンが過剰に蓄積し、特に筋肉、心臓、肝臓の細胞などにたまります。筋肉の細胞にグリコーゲンがたまると、細胞が損傷を受けて、筋肉が正常に機能できなくなります。
そのため、以下のような症状が現れます。症状やその程度は人により異なります。
- 筋力の低下
- 発達や成長の遅れ
- 呼吸困難
- 心機能障害
- 背骨の湾曲
ムコ多糖症Ⅶ型(スライ病)
ムコ多糖症は7つの型に分類され、それぞれの型の症状は異なります。共通する症状としては、関節の拘縮、骨格変形、低身長、特徴的な顔貌、巨舌、厚い皮膚、多毛、気道狭窄、反復性呼吸器感染、難聴、心臓弁膜症、お腹の膨れ(肝脾腫)、臍・そけいヘルニア、中枢神経障害などがあります。
ムコ多糖症Ⅶ型(スライ病)は、生まれつき、βグルクロニダーゼという酵素を十分に持っていないために起こります。
デルマタン硫酸、コンドロイチン硫酸、ヘパラン硫 酸というムコ多糖の分解が阻害され、体内の細胞組織に蓄積します。
そのため、多系統の組織や臓器に障害が生じ、以下のような症状が現れます。
症状やその程度は人により異なります
- 特徴的な顔貌
- 肺疾患
- 心機能障害
- 肝臓や脾臓の腫大
- 関節の拘縮
- 低身長
- 精神運動発達遅滞
- 多彩な骨形成異常
